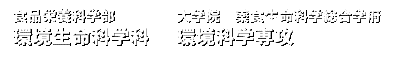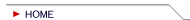Interdisciplinary Symposium on Environmental Sciencesに参加して
助教(転出) 榊原 啓之 (Assist.Prof. Hiroyuki SAKAKIBARA)2008年11月11−13日に愛媛県は松山市で開催された表題のシンポジウムに参加してきた。本リレーコラムのバトンを受け継いで、「さて、何についてコラムろうか?」と思い悩んだが、このネタが一番にホットであると思い、参加報告&回想を書かせてもらう。ご興味があれば、暫しお時間いただきたい。
― 10年のブランク ―
1997年頃の小生は、愛媛大学農学部環境化学研究室で卒業研究の真最中であった。研究テーマは、「海ガメ中のヒ素の形態分析」だったと思う。当時は、まだ“ヒ素”という言葉が現在ほど市民権を得ておらず、テーマとして“ヒ素”をいただいた時には、「“ヒ素”ってなんなん?」などと、内心では思ったことを記憶している。しかしながら、“ヒ素”について調べれば調べるほど、その性格にのめり込んでしまった。例えば、
- ヒ素は毒である。でも、その毒性は存在形態に依存している。
- 中には、毒性を有しない(極めて低い)ヒ素化合物が存在する。
- 色々な興味深い歴史的背景がある。例えば、ナポレオンのヒ素毒殺説。
- ある疾患(急性前骨髄球性白血病)の治療薬となりうる。
- ヒジキ等の海藻類に豊富に含まれている。
- etc。。。
(贔屓しているだけかもしれないが)これだけ様々な表情を持つ元素は他には例がなく、真剣にヒ素科学者になることを夢見て、同級生たちには「将来、俺はヒ素科学者になったら、いずれは“ヒ素のヒソヒソ話”って一般本を書くぞ!」などと本気で夢を語っていた。まあ、その夢は志半ばで潰えてしまったが、10年経過した今思い返しても、興味深い元素には違いない。さて、余談が長くなってしまった。本題にもどることにしよう。
小生は、大学院からはヒ素のテーマを離れて、遺伝子変異やストレスの研究にのめりこみ、それとともに愛媛から離れることになった。そして卒業後10年間、研究室に顔を出す機会もなかった。研究分野も異なってしまったので、出席する学会も一緒になることはなく、先生・先輩・同輩・後輩達とお会いする機会も極めて少なくなっていった(あまり良い卒室生とは言えない)。そんな中、今回10年ぶりに松山でゆっくりと過ごせる機会を得たわけである。しかしながら、この10年間は、あまりにもブランクとしては長かったようだ。会場は、愛媛大学構内に新しく建てられたセンター内だったのだが、そこはもともとグラウンドであった。硬式庭球部に在籍していた私にとっては、汗水垂らしてランニングした思い出深い場所だったはずなのだが、その面影はすでにない。私が4年間を過ごしたアパートは取り壊されて駐車場となっていたし、行き付けの定食屋や飲み屋、銭湯は軒並み暖簾を下ろしていた。よく利用していたスーパーは辛うじて残っていたが、それでも外観は色あせてしまって(失礼)、近所にできた新しいスーパーの勢力に押されているのは明らかである。街中の有名な待ち合わせ場所は、シャッターを下ろしてしまって、今は取り壊されるのを待つ状態。家が並んでいた場所に道路が通っていたり、道後温泉の前が歩行者専用道路となっていたり・・・。ここ10年における松山の様変わり具合に、ある種の驚愕を覚えた小生であった。
そんな中で、変わらず色褪せないモノがあった。“ヒト”である。もちろんお互い見た目は変わるし、“Nature誌”の筆頭著者となり今を時めいている同期、潤沢な研究費に恵まれて最先端の研究に没頭している先輩、留学生として日本にやってきてそのままポストを得て日本で研究を続けている先輩や自国に戻って要職に就いている先輩、片や若くして研究室を構えたものの思い通りの研究ができないことで悩む同期、、、とそのヒトが置かれているポジションも変わった。しかしながら、それぞれのヒトにそれぞれの10年があったけれども、(当たり前かもしれないが)そのヒト自身、あるいはそのヒトとの思い出は変わらない。10年を経ていろいろなヒトの“今”があるのだけれども、根底にあるのは学生時代であり、そこがすべてのスタートであることを、思い出話に花を咲かせながら、改めて痛切に認識していた。
研究室に配属された学生さん達にとって、研究室内で過ごす時間は、親兄弟恋人達と過ごす時間よりも遙かに長い(はず)。そのような貴重な時間の中で、自分の研究の進展も確かに重要であるが、先輩・同期・後輩との出会いを楽しめるゆとりを持つことも同じくらい大切であることを私は学生たちに伝えることができているのだろうかと、ふと考える。私が卒業した研究室のように学生数が常時20名を超えるような大所帯の研究室ならいざ知らず、学生数が減りつつある昨今では、研究室内にとどまらず、専攻内、学科内、大学内あるいは大学間で出会う機会も大切だろう。そこから様々な人間関係を構築し、10年後、20年後の糧に育てていく環境を提供することも私の勤めの一つじゃないのかと、気持ちを新たにした次第である。
―勝負師―
今回のシンポジウム期間中に訪問したセンター内に、次の様な印象深い言葉が入ったポスターが貼ってあった。
『剛腕の勝負師』
これは愛媛大学グローバルCOEプログラムの拠点リーダーである田辺信介教授を評した文言であるが、確かに“剛腕”というイメージはピッタリだと思う。そして、“勝負師”との言葉が私には非常に新鮮であった。“勝負師”との言葉は普段の生活でもよく耳にするが、どちらかというとスポーツや博打の場ではなかろうか?そこで“勝負師”を広辞苑で調べると、「いちかばちか、重大な事の成否をかけて大胆にことを行う人」とある。なるほど、、、勝負師でもある研究者か。見事な表現ではなかろうか。
数多くの論文が日々報告されているが、その大部分が“銅鉄論文”と言われる。銅鉄論文とは、「鉄を加えたら、A反応が生じる」との論文が初めて公表された後に続く、「(鉄じゃなく)銅を加えても、A反応が生じる」といった、ある種の「手を変え品を変え」論文群を指す。このような銅鉄論文の作成に精を出すヒトは、研究者であっても勝負師ではない(と私は思う)。かく言う私も、新しい研究戦略を練る時に、「今どのような研究がホットなのか」と流行に走ってしまい、「今はあまり流行っていないが、10年後にブレイクするかもしれない新しい研究」というある種の博打的要素を含んだ研究テーマは、考えることはあってもなかなか実行に移せない(情けない話である)。恐らく、ノーベル賞クラスの研究をなされている研究者は皆、勝負師なのであろう。それほど長くはない私の研究者人生、どこかで“勝負師”になってみたいものである。今、その種は、、、頭の片隅で発芽の期を心待ちにしている(はずである)。
― おわりに ―
結局、シンポジウムの内容に関しては、まったく触れることができなかったこと、申し訳なく思う。
(以上)
>>次のコラム: -第4回- 「「カニと化粧品」のはなし」 吉岡 寿