静岡県立大学”食品生命科学科”はこんな方を求めています!
静岡県立大学”食品生命科学科”はこんな方を求めています!
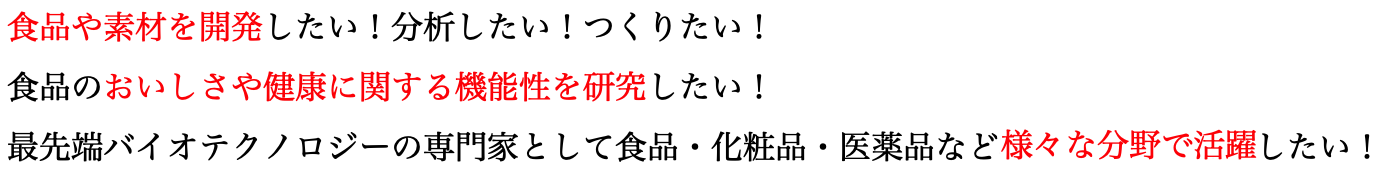
食品や素材を開発したい!分析したい!つくりたい!
食品のおいしさや健康に関する機能性を研究したい!
最先端バイオテクノロジーの専門家として食品・化粧品、医薬品など様々な分野で活躍したい!
学科の概要
学科の概要
食品生命科学科は、食品産業を中心に化粧品や医薬品産業など様々な分野で活躍できる、食品科学とバイオテクノロジーの両方の専門知識・技術を身につけた人材を育成しています。身近な食から最先端の科学技術まで、幅広く学べる点が強みです。
食品生命科学科は、食品産業を中心に化粧品や医薬品産業など様々な分野で活躍できる、食品科学とバイオテクノロジーの両方の専門知識・技術を身につけた人材を育成しています。身近な食から最先端の科学技術まで、幅広く学べる点が強みです。
「ものつくりの県」静岡で食品を学ぶ
「ものつくりの県」静岡で食品を学ぶ

※静岡は人口370万人(福岡に次ぐ全国第10位)の県で、人口構成やバラエティに富んだ産業構造、風土などから「日本の縮図」とも呼ばれています。その特性から、新商品が全国発売される前に販売テスト場所として頻繁に選ばれることも有名です。
静岡は全国トップクラスの健康長寿の県としても知られ、お茶やみかん、魚介類などの地域資源を活用することで、機能性食品を中心とする多くの高付加価値食品が開発されてきました。静岡県立大学 食品生命科学科には、静岡県が推進しているフーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクトの一員として、国の食品産業拠点を支える学術基盤としての役割が期待されています。食品産業の中心地ともいえる場所 で食と生命の科学を学ぶことは、静岡でしか経験できない大きな価値と魅力です。

※静岡は人口370万人(福岡に次ぐ全国第10位)の県で、人口構成やバラエティに富んだ産業構造、風土などから「日本の縮図」とも呼ばれています。その特性から、新商品が全国発売される前に販売テスト場所として頻繁に選ばれることも有名です。
静岡は全国トップクラスの健康長寿の県としても知られ、お茶やみかん、魚介類などの地域資源を活用することで、機能性食品を中心とする多くの高付加価値食品が開発されてきました。静岡県立大学 食品生命科学科には、静岡県が推進しているフーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクトの一員として、国の食品産業拠点を支える学術基盤としての役割が期待されています。食品産業の中心地ともいえる場所で食と生命の科学を学ぶことは、静岡でしか経験できない大きな価値と魅力です。
学科長インタビュー
学科長インタビュー

19世紀頃に報告された有機化学の研究成果を見ると、新しく発見された化合物とともに味が記載されています。性質のよく分からない成分を研究者が味見する、まさに命がけの仕事です。
このような話は、化学の世界だけのことでしょうか?食生活においても同じことが言えます。先人たちが色々なものを口にして安全な食品を見つけ出し、それが蓄積されて食文化となり、現在の私たちは安心して食事を摂ることができます。これは、食品に含まれている成分を知ることに繋がります。
食品には未知の成分や機能性の分からない成分など、まだまだ多く存在しています。知られている成分でも、保存や加工についてより良い方法があるかもしれません。食品生命科学科では「食品成分を知る」を目指して、食に関する様々な教育・研究を行っています。安心でより充実した食生活を創り出していくために、一緒に学んでいきましょう。

19世紀頃に報告された有機化学の研究成果を見ると、新しく発見された化合物とともに味が記載されています。性質のよく分からない成分を研究者が味見する、まさに命がけの仕事です。
このような話は、化学の世界だけのことでしょうか?食生活においても同じことが言えます。先人たちが色々なものを口にして安全な食品を見つけ出し、それが蓄積されて食文化となり、現在の私たちは安心して食事を摂ることができます。これは、食品に含まれている成分を知ることに繋がります。
食品には未知の成分や機能性の分からない成分など、まだまだ多く存在しています。知られている成分でも、保存や加工についてより良い方法があるかもしれません。食品生命科学科では「食品成分を知る」を目指して、食に関する様々な教育・研究を行っています。安心でより充実した食生活を創り出していくために、一緒に学んでいきましょう。
