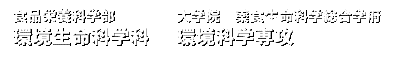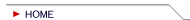“体の中の外”について
教授 桑原 厚和 (Prof. Atsukazu Kuwahara)環境生理学研究室
1.はじめに
私の専門は、消化管の生理学です。では、生理学とはどのようなことを研究する学問分野なのでしょうか。少し時間をさかのぼり歴史的に考えてみますと、紀元前4−500年頃にギリシャにその起源を求めることができる自然学の発生に辿りつきます。その当時の哲学者たちが最も関心を持ったのは、万物の根源と宇宙の構造であったと言われています。このようなことを調べようとして発生したのが「自然学」、ピュシス phusis (「生む」 phuo という動詞に由来)の学と呼ばれたものです。物理学 physics や生理学 physiology の語は「ピュシスの学」が形を変えたものですが、言葉だけではなく、このイオニアの自然学が、将来の物理学や生理学の母体となったのです。私たちの体の中で起こっている生命現象は形態と機能の両面から理解することが不可欠であり、形態を主に扱う学問が後に形態学 morphology として独立していきます。さらに、その後、体を構成する物質の分離同定を主な目標として生化学が独立していきます。現在の狭い範囲で言うところの生理学とは、私たちの体の正常な機能がどのように制御されているのかを主に物理化学的手法を用いて研究しようとする基礎科学の分野であるということが言えます。しかしながら、学問の発展に伴う専門の細分化のために、現在では生体過程の異なる側面を総合的に考えて生体全体の機能を理解しようとする視点がおろそかになる傾向が顕著になってきています。そこで、近年、本来の生理学の成り立ちに立ち返って、形態学、生化学および狭義の生理学を合わせた生理科学 physiological sciences により生命現象を理解しようとする試みが始まっています。生理学でもっとも基本的概念の一つにホメオスタシス homeostasis があります。ホメオ homeo は「似ている」を意味し、スタシス stasis は「停滞」を意味します。したがってホメオスタシスとは「停滞に似た状態」という意味になりますが、実際にはいくつかの互いに影響しあう系の間で特定の生理的変数値(例えば、体温や血圧)がほぼ一定に保たれている状態をいいます。つまり、いくつかの組織や器官の基本的機能がうまく組み合わさって、その結果、高次の機能が調和して発揮できるように私たちの体はなっているわけです。極端な言い方をすると、ホメオスタシスが破たんすると病気が発生するということになります。このような概念は、19世紀のフランスの有名な生理学者クロード・ベルナール Claude Bernard により提唱されました1)。ベルナールにより提唱された「内部環境の恒常性 la fixite de milieu interieur 」という概念をさらに発展させたのがアメリカの生理学者であるウォルター・キャノン Walter B. Cannon であり、彼によりホメオスタシス homeostasis という言葉が作られました2)。つまり、消化管の生理学とは消化管の恒常性がどのようなしくみで制御されているかを研究しようとする生理科学の一分野になるわけです。
2.消化管といわゆる「環境」との関わりについて
このような学問的背景に基づき私の専門分野である消化管の生理学と環境とのかかわりについてお話したいと思います。皆さんは消化管をどのように捉えているでしょうか?あるいは、消化管を研究している先生がどうして環境科学研究所にいるのかなと不思議に思われるかもしれません。しかし、私たちの体の構造良く考えてみてください。私たちの消化管は口と肛門によって外界とつながっています。これは何人たりとも否定することができません。また、私たちは外界と接する消化管を通して毎日、エネルギー源としての食物を摂取しなければならないわけですが、その時同時に私たちの体内には生体にとり有害な物質を外部環境から取り込んでしまう可能性があります。つまり、消化管の機能は、生体にとって必要な栄養素や・電解質(イオン)などを外部環境から内部環境に取り込むことにあります。また、同時に生体にとって有害な病原微生物や有害物質を排除するという機能も併せ持っているわけです。そこで、消化管には、外部環境と接している消化管の内側(消化管内腔)の状況を常にモニターするための装置が備わっているのです。それには、中枢神経系に存在する神経細胞数にも匹敵し、かつ中枢神経糸とは独立した(1)腸管神経系、多くの消化管ンホルモンを分泌する腸内分泌細胞を有するため体の中で最大の内分泌器官とも考えられる(2)腸内分泌系、さらには消化管の免疫系を制御する(3)腸管免疫系などの装置があります。これらが協調して消化管の働きを制御しているわけです。今回は、まず消化管の壁に埋め込まれているセンサーにどのようなものがあり、それらがどのようなものを監視しているのかについて私たちの研究を中心にお話したいと思います。
3.消化管の構造とセンサー
消化管は口と肛門により外部環境とつながっているわけですが、その構造は基本的にはどの部分をとっても同じ構造をしています。食べ物が通る一番内側に細胞が一層並んでいる上皮細胞層があります。 細胞とは私たちの体を構成する最小単位のことです。この細胞層を通して各種の栄養素やイオンが輸送されるわけです。この細胞層があるおかげで外部環境と通じている消化管内腔から、多くの有害な微生物や大きな分子の体内への侵入を防ぐことができるのです。また、この細胞層には多くの栄養素を吸収したりイオンを輸送するための分子素子(輸送体やイオンチャネル)が発現しています。その下に粘膜固有層というものがあり、多くの免疫系を担当する細胞が存在しています。さらに、その下に粘膜筋板という組織があります。それから粘膜下組織、平滑筋層、漿膜という構造になります。皆さんも想像がつくと思いますが、センサー(受容体)は粘膜上皮内に多くの場合は存在します。なぜならば、消化管を通過したり消化管の中で新しく作られるいろいろな化学物質をモニターしなければならないからです。
最近、胃に「うま味成分」の本体であるグルタミン酸塩を受容するための受容体が胃底腺を構成する主細胞の管腔側、つまり食べ物が通る側に発現していることが報告されました3)。胃底腺と言うのは、胃の壁にある無数の縦穴、これを胃小窩と呼びますが、その底に長い管状の構造物があります。これが胃底腺で胃酸だとかペプシンと言う消化酵素と粘液などを分泌する壁細胞や主細胞および副細胞から構成されています。主細胞には胃酸と反応してたんぱく質を分解するための酵素であるペプシンの素となるペプシノーゲンが多く含まれますが、食事と共に胃に取り込まれたグルタミン酸塩は、主細胞上のうまみ受容体に結合することでペプシノーゲンの転写因子に影響し、胃でのタンパク質消化に関与しているのではないかと、この受容体を発見したグループの人たちは考えているようです。ちなみに副細胞からは胃壁を保護するためのアルカリ性粘液を分泌する細胞です。もう一つ重要なセンサ―がありますが、これは食事により胃が膨らんだ時などに機械的受容体として働くもので、この種のセンサーにはセロトニンと言う物質が含まれています。この受容体細胞は直接胃の内腔面に顔を出しているわけではないので閉鎖型の腸内分泌細胞とも呼ばれています。
ここまでは、胃でのセンサーのお話でしたが、小腸に入ると胃では分解されなかった脂肪などを受容するようなセンサーの存在が言われていますが、私の知る限り、現在のところその実態はあまり明らかではありません。
やっとここからが私たちの教室でここ数年間かけてやってきた仕事のご紹介です。ここで、少しは生理学と環境との関係が説明できるかもしれません。食物がいったん胃腸管に入ってしまえば、私たちはその味を意識することはありません。しかしながら、消化に伴い産生される多くの化学物質が消化管の生理応答を誘発することは古くから知られていたことで、この生理応答に各種の消化管ホルモンを分泌する腸内分泌細胞が化学物質を受容するためのセンサー細胞として機能しているのではないかと考えられてきました。しかしながら、現在でも、どのタイプの内分泌細胞がどのような化学物質を受容するのかということについては、小腸ではブドウ糖の受容機構以外はほとんどわかっていません。
そこで、私たちは、大腸には多くの腸内細菌が存在し、私たちの体内で消化管と相互に影響しながら一種の生態系を構築しているということに着目しました。このとは、生体にとって外部である消化管管腔に存在する腸内細菌が消化管の生理機能に何らかの形で影響しているのではないかということを想像させます。次に私たちが考えたことは、小腸で消化を免れた未消化物が大腸に侵入し腸内細菌により短鎖脂肪酸が作られることに着目しました。ちょうどその頃、2003年ですけれど短鎖脂肪酸の受容体の存在が報告されました4,5)。そこで、生理学実験と並行させながら、生理反応の空間的基盤を提供する形態学データを収集するために新しく発見された短鎖脂肪酸受容体の抗体の作成に着手しました。そしてその抗体を使い短鎖脂肪酸受容体のひとつ、GPR43がヒトやラットの粘膜上皮に存在するペプチドYY(PYY)と言う消化管ホルモンを分泌するL型の腸内分泌細胞に発現することを明らかにしました6,7)。また、生理学実験と併せて考えて、これらの受容体は十分大腸の管腔内に存在する短鎖脂肪酸を受容するためのセンサーとして機能しているのではないかと考えました。しかしながら、この受容体には2種類(GPR41とGPR43)あり、なぜ受容体が2種類存在し、どのように別々に働いているのかなどと言ったことはまだ明らかではありません。また、最近では短鎖脂肪酸のもう一つの受容体であるGPR41にはPYY以外にも別の消化管ホルモンが含まれていることを見つけました。だんだん長くなってきましたが、私たちの研究室では大腸に苦味を感知するセンサーが存在し、そのセンサーを介して大腸の機能が制御されている可能性についても明らかにしています8)。簡単に述べますと、食生活の欧米化に伴い高タンパク・高脂肪食を私たちは多く摂取するようになってきました。そうしますと脂肪を消化するために胆のうから多くの胆汁が分泌されます。胆汁とは、皆さんご存知のように“熊の胆”と同じもので苦い物質です。この胆汁は脂肪を消化する手助けをします。普通、分泌された胆汁のほとんどは腸肝循環により回腸末端で胆汁の輸送体により吸収され大腸に侵入することは稀です。しかしながら、腸肝循環により再回収ができなかった胆汁は、大腸に侵入して腸内細菌に利用されます。この腸内細菌に利用された胆汁が2次胆汁酸となり、これが大腸がんを誘発するのではないかとの報告もあります。先ほど述べましたように、胆汁は苦いことが知られていますが、乱暴な言い方をしますと大腸にある苦味受容体もこの苦味物質である胆汁酸塩を感知して、無意識化のうちに体にとって有害であるということを認識し、それを早く体外へ排除するために軽い下痢を起こしているのではないかと私たちは想像しています。このように、消化管の内腔は私たちにとっては外部環境にあたり、ここでお話ししましたような化学受容センサーが常に体内の外部環境をモニターして私たちの健康を維持しているのではないかと考えられます。
4.おわりに
私たちは、常に私たちを取り巻く環境に依存しながら進化してきたことが考えられます。その過程で、消化管内腔には私たちの体の中に取り込んだ外部環境をモニターするための各種のセンサーが備わってきたのではないでしょうか。そうでなければ、私たちの体のダイナミックな生理機能として良いものを選択的に取り込み、また病原体のように有害なものだけを選択的に排除するという機構も生まれなかったはずですし、このような機構を私たちが外部環境の刺激により獲得することで私たちは地球環境に適応して生存できてきたのだと思います。このような観点から、私見ですが環境科学というものは何でも包括してやっていける学際的学問だと思っています。とりとめのないことを書きましたが、どの分野でも何かを排除しようとするところには新しいものは生まれてこないのではと私は思っています。
このコラムでは私のよって立つ研究分野の歴史の一端をご紹介しました。私の大学での在職期間もあと10年を切りましたが、これからもいわゆる“環境に取り囲まれた小宇宙である生体の神秘”について研究できればと思っています。
引用文献
- 「実験医学序説」 岩波書店、 1938(初訳)、1970(改訳). (原典: In troduction a l'Etude de la Medecine Experimentale. 1865.)
- 「体の知恵 ―この不思議なはたらき」 講談社学術文庫、 1981. (原典: Wisdom of the Body. 1932)
- mGluR1 in the fundic glands of rat stomach. FEBS Lett 581: 1119-1123, 2007.
- The Orphan G protein-coupled receptors GPR41 and GPR43 are activated by propionate and other short chain carboxylic acids. J Biol Chem 278: 11312-11319, 2003.
- Functional characterization of human receptors for short chain fatty acids and their role in polymorphonuclear cell activation. J Biol Chem 278: 25481-25489, 2003.
- The short chain fatty acid receptor, GPR43, is expressed by enteroendocrine cells and mucosal mast cells in the rat intestine. Cell Tissue Res 324: 353-360, 2006.
- Expression of the short-chain fatty acid receptor, GPR43, in the human colon. J Mol Histol 39: 135-142, 2008.
- Secretory effects of a luminal bitter tastant and expressions of bitter taste receptors, T2Rs, in the human and rat large intestine. Am J Physiol in press 2009.
参考文献
- 「医学の歴史」 梶田 昭 著 講談社学術文庫 2008
- 「細胞紳士録」 藤田恒夫・牛木辰男 著 岩波新書 2007
- 「標準生理学 第6版」 本郷利憲・広重 力・豊田順一 監修 医学書院 2005
(以上)
>>次のコラム: -第8回- 「持続可能なエビ養殖を目指して in ベトナム」 内藤 博敬
>>ひとつ前のコラム: -第6回- 「論文掲載までの舞台裏−ぬっきー Effectがもたらした Casual Discovery −」 豊岡 達士